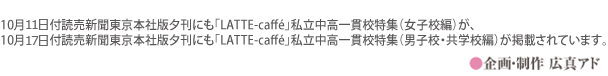安田教育研究所 代表安田 理氏
〇全体動向 2014年3月の首都圏の小学校卒業者数は前年より1900名ほど減ります。それと、アベノミクス効果で景気が上向いていると言われますが、ご家庭にはまだそれが波及していず、一部の富裕層をのぞいて財布事情は厳しいのが現実です。そのため中学受験率はこのところ少しずつ低下してきています。
ですから2014年は珍しく首都圏では私立中学の新規開校は1校もありませんが、受験生・ご家庭にとっては「広き門」になり、幸いな年になります(公立中高一貫校は1校(川崎市立川崎高等学校附属)が開校します)。
保護者の方も日々お感じになられていると思いますが、このところ経済面だけでなく、社会の様々な場面でグローバル化が急速に進展しています。これからわが子が巣立っていく社会は厳しく、また変化が多いと思われます。それだけに、わが子にどんな変化にも対応できるだけのきちんとした学力、異なる背景を持った人とも協力して仕事していけるだけの資質・能力をつけておくことが欠かせません。
そうしたことまで考えている保護者が少なからずいます。小学校卒業者数が前年より1900名も減っているにもかかわらず、3大模試の受験者数は4%程度の減にとどまっているのは、そうした背景があるからでしょう。 わが子に自分の力で生きていけるだけの力をつけておいてやりたいと願う保護者が私立中学を選んでいるのです。
〇おもな動向 ここからは3大模試の志望者数から見られる2014年度入試の傾向について男女別・日程別に述べてみましょう。
<男子>- 1月中 1月10日~12日は栄東、開智に集中化現象
2014年度入試では開智がはじめて埼玉の解禁日である1月10日に先端Aの入試を行う。またこれまで16日に行っていた一貫②も12日に動かして1月10日~12日は毎日入試を設定した。これに対抗して栄東は1月10日のAで、難関大コースばかりでなく東大選抜の合格者も発表することに。男子はいまのところこの2校に受験生の志望が集まっている。 - 2月1日 自主性に任せるタイプの学校が志望者増
ここ数年、しっかり勉強させるタイプの学校が人気で、自由で生徒の自主性に任せるタイプの学校は敬遠されてきたが、今年は麻布、武蔵、桐朋がいずれも志望者が増えている。
早稲田①、慶應普通部、早稲田実業がいずれも減少しており、付属校敬遠の動きは2014年度入試でも続きそうだ。逆に言えばねらい目になる。 - 2月2日 この日も付属校はねらい目になりそう
この日も明治系、法政系、中央系、慶応湘南藤沢、立教池袋①、学習院①が入試を構えている。青山学院が3日に移った分、他の付属校の志望者が増えてよさそうだが、増えているのは立教池袋①と法政第二①だけ。2日も付属校はねらい目になりそうだ。 - 2月3日 公立中高一貫校は都内と3県で差が
東京の公立中高一貫校は志望者が増えているが、他は神奈川の3校を含め減少気味。来年開校する川崎市立高校附属もまだ志望者は多くない。
<女子>
- 1月中 千葉の減少傾向に歯止めがかかる
淑徳与野①、江戸川取手①、栄東(東大Ⅰ)が2年連続して志望者が増えている。栄東(東大Ⅰ)は男子でも2年連続。1月入試は最近は埼玉の受験者数が増加傾向で千葉が減少傾向にあるが、2014年度入試では千葉が盛り返しそう。 - 2月1日 神奈川の受験生は地元がねらい目
横浜女子御三家は、フェリス女学院、横浜共立学園A、横浜雙葉の3校もと減少。交通機関の発達で上位生が神奈川から東京へ抜けている可能性がある。神奈川生にとっては地元がねらい目になりそうだ。2013年度入試で女子校でもっとも受験者が増えたのが山脇学園だが、2014年度入試でもさらに増えそうだ。 - 2月2日 大きな変化のある学校が注目を集めている
2月2日が日曜に当たることから午後入試に移した恵泉女学園②、2013年度入試から午後にした東京女学館一般②が大人気。これまで3日に行っていたものを前倒しした品川女子学院②も志納者増。大きな変化は注目を集めやすい。 - 2月3日 付属色の強い学校が人気
この日の特徴は、青山学院、中大附属横浜③、慶應中等部、日本女子大附②、昭和女子大附Cと、付属色の強い学校が志望者を増やしていること。男子では見られない現象だ。
受験に成功するかどうかは、「その学校に入りたいという気持ちがどれだけ強いか」にかかっています。自分が本当にその学校に行きたくなれば勉強に対する姿勢が変わってくるのです。
本人の中に「その学校に行きたい」という気持ちをどう作るかが、親の腕の見せ所。偏差値表を見せて「こっちのほうが高いわよ」、大学合格実績を比較して「こっちのほうが難関大学に進めそうよ」-そうしたやり方をしているご家庭もあると思います。が、こうしたやり方は、純粋な子どもたちは共感しません、むしろ反発する可能性があります。
それよりもその学校が持っている優れた教育上の工夫、生徒への温かなアプローチ、生き生きしている在校生の姿……そうしたもののほうが子どもは学校にいい印象を持つものです。それには親自身がそうしたものに気づく目を持たなければなりません。「偏差値」や「大学合格実績」といった数字は誰だって判断できる材料です。せっかく受験にコミットしているのですから、少しは「プロ」として腕を振るってみてはどうでしょう。自分自身の目で各学校の良さを発見してください。
それを基に、複数の中から子どもに選択させるようにもっていくようにしてはどうでしょうか。つまり候補となる学校は親が選ぶが、最終的な受験校は子どもが自分で決めたというかたちをとるのです。
どんなところに進んでも、入学後必ず不本意なことに出会います。そのときそれを乗り越えられるのは、自分が選んだ学校だからです。自分で選んだのであれば、自分の責任。他に転嫁することはできないから、なんとなくがんばれるものです。親に強制された学校ではそうはいかないことがよくあることを知っていただきたいと思います。