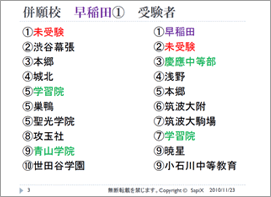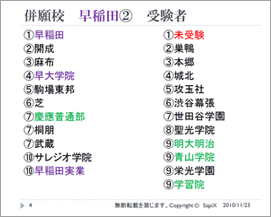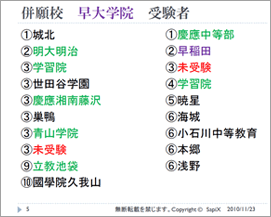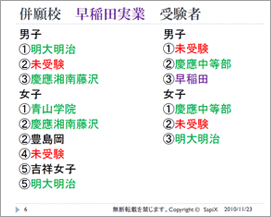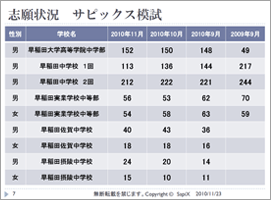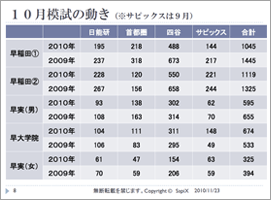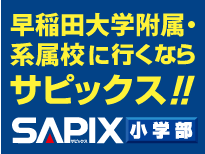早稲田中では算数、理科で差がつく
森上 首都圏にある早稲田附属・系属中学3校(以下、早稲田中、早実、早大学院と記載)の入試について、様々な角度から分析していきたいと思います。まず、2010年入試でどのような動きを見せたのか、早稲田中から分析をお願いします。
広野 早稲田中入試の配点は、算数・国語が各60点、理科・社会が各40点と、算数・国語のウエートが高くなっています。同校では教科ごとに受験者平均点、合格者平均点が公表されているのでどの教科で差がついているのか、明確に分かります。資料の通り、算数、理科で大きな差が見られますね。とくに算数の第1回は、受験者平均点23.8点に対して、合格者平均点は33.0点と、10点近くの差が開いています。
森上 算数の得点力が備わっていなければ、合格が難しい中学といえそうです。早実はいかがですか。
広野 注意しておきたいのは、この3校でそれぞれ配点が大きく異なっていることです。早実は、算数・国語各100点、理科・社会各50点と、早稲田中以上に算数・国語のウエートが高めです。一方で、早大学院は算数・国語各100点、理科・社会各80点と、4教科のバランスのとれた子どもが有利になっています。それぞれの配点にあわせた対策が必要になるでしょう。
また、早実の合格最低点を見ると、男子の192点に対して、女子は206点と、女子の方が高い得点を要求されています。女子にとってはかなり狭き門だったといえます。
森上 早実は、共学校になって以降、学校生活において女子生徒がリーダーシップを発揮しているシーンが数多く見られると聞いています。そんな女子のパワーが入試面にも反映されている気がします。早大学院は、2010年が中学部初の入試ということもあって、まだ細かなデータは公表されていません。今後、志望校選択の一助となるように、情報の公開を期待しています。
解き方の欄がない早稲田中、早実の算数では正確性が要求される
森上 次に、算数、国語の入試問題の特徴を見てみましょう。
広野 実は、解答用紙には出題分野や問題の難易度以上に、その学校が求める能力があらわれていることが多いのです。早稲田中(第1回)の解答用紙で特徴的なのは、解答のみを答えさせる形式で、解き方の欄がないことです。子どもの中には、式を書くのが苦手で、試行錯誤しているうちに、いつのまにか答えが出ているというタイプもいます。そういう子どもは、自分に向いている入試問題だと考えがちかもしれませんが、解き方の欄がないということは、部分点がもらえないということでもあります。丁寧に解いて、正確に計算して、完全な答えを導き出さなければならないわけで、むしろ厳しい入試といえるでしょう。しかも、算数の得意な子どもばかりが受験しているにもかかわらず、平均点は低く、相当な難問が出されることを覚悟しておく必要があります。
森上 私は早稲田中の出身者をたくさん見ていますが、共通するのはコツコツ真面目に取り組むタイプが多いということです。入試問題の形式も関係しているのかもしれません。
広野 早実の算数も、解答のみを答える形式で、解き方の欄がありません。同校は、男子校時代は算数・国語の2教科型で、算数の問題が難しい学校として定評がありました。共学化と同時に4教科型になるとともに、女子受験生に配慮して算数の問題はやや易化するのではないかという期待感もありました。けれども、妥協のないハードな問題を出すという姿勢は堅持されています。一般的な女子校入試に多い基本的なパターン問題の学習だけでは、この入試問題に対処するのは困難で、難関男子校並みのハードな問題に慣れておくことが大切です。
森上 早大学院の算数は比較的取り組みやすい問題だったと聞いていますが……。
広野 受験生のレベルを考えると、少しやさしいのではないかという印象がありました。
けれども、初年度でしたから、まだ傾向が確立されたわけではありません。初年度の状況を踏まえて、2011年度はやや難しい問題が増える可能性もあると考えています。また、他の2校との大きな違いは、式の欄があることで、思考のプロセスを意識しながら解いていく必要があるでしょう。
森上 国語の入試問題の特徴もお願いします。
広野 近年、男子校、女子校を問わず、難関校の国語では記述問題が増えています。100~120字の長めの記述を要求されるケースも見られます。対して、この3校では、記述問題はそれほど多くありません。その分、与えられた問題文をきちんと読み込み、正確に読解した上で解くオーソドックスな国語力が求められます。知識問題、記号選択問題もバランスよく出題されており、日頃の実力がストレートに反映される、得点差がつきやすい問題でもあるのです。
早稲田中は進学校、早実・早大学院は大学附属校との併願が多い
森上 次に、合格者の成績分布を見てみましょう。
<資料1>は、各校に合格したサピックス小学部の子どもたちの偏差値をまとめたものです。サピックスは難関校志望者が多く、偏差値が低めに出ますから、他塾に通われている場合は、この偏差値に7~8プラスすれば目安になるでしょう。
広野 サピックスでは昨年、6年生の2学期以降に5回の実力テストを実施しました。この資料の偏差値はその平均です。合格率80%以上が緑、50~80%が黄、それ以下が白と、3つのゾーンに色分けしてあります。2010年度に関しては、早稲田中の第2回、早実の女子が突出して難しく、次いで早稲田中の第1回、早実の男子が続いている状況です。
森上 早大学院の初年度入試は、意外に競争率が低くやや入りやすい状況があったようですね。
その反動から、後述するように、2011年度は大幅な難化が予想されています。併願校の傾向はどうなっていますか。
広野 <資料2>は、サピックス小学部で早稲田中第1回(2月1日)を受験した子どもの併願校です。
左が2月2日、右が2月3日に受験した学校ですが、まず目立つのは「未受験」が上位にきていること。早稲田中が本命で、他の選択肢は考えていないケースがけっこう見られるわけです。
おそらくこの場合は、千葉、埼玉の有力校、あるいは早稲田佐賀、早稲田摂陵など、1月中に合格校を確保している受験生もいるでしょう。
もう1つ併願校として多いのが、本郷、城北、巣鴨、浅野など、面倒見の良さに定評のある進学校です。つまり、早稲田中の志望者は、「完全第一志望層」と「進学校の1つとして捉えている層」に大別されるわけです。<資料3>の第2回(2月3日)の併願校(左が2月1日、右が2月2日)を見ても、早稲田3校のみの併願で、それ以外は受験しない層と、超難関進学校と併願する層の2パターンに大別されていることが分かります。
森上 早稲田中は戦前からの有名な進学校で、現在でも東大に2ケタの合格者を輩出しています。
附属校的な協調的学風というよりも、進学校的な競争的学風が根強く、それが進学校との併願が多い要因になっていると思われます。
広野 それに対して、早大学院は趣が異なり、併願校に他大学附属校がズラリと並んでいます。
<資料4>。早実も、未受験もしくは他大学附属校との併願が主流です<資料5>。ハードな受験勉強を経験するのは中学入試までで、中学入学後は大学までのルートが確保された中で、伸び伸びと過ごしてほしいという意識があらわれているのでしょう。
森上 2010年度の大学入試では、明治大の総志願者数が早稲田大を上回るなど、明治人気が上昇しています。早大学院、早実の併願校の上位に明大明治がランクインしているのは、その人気が反映していると考えられます。
2011年度は早大学院の志願者数大幅アップの可能性大
森上 さて、2011年度はどのような動きを見せるのでしょうか。全体的な注目点から聞かせてください。
広野 まず、開智未来、二松学舎柏、千葉明徳の3校の新設があります。横浜山手、目黒学院、貞静学園、横浜翠陵と、共学化の流れも進行中です。
大きな話題になっているのが、海城の高校募集停止と、第1回・第2回の募集人員を5名ずつ増やすことで、人気を集めています。大学系列化の動きも続いており、中央大が横浜山手を、東洋大が京北を系列化します。それから、例年、前年の合格実績、とくに東大合格者が大幅に増えた学校が人気になる傾向も顕著です。2011年度は聖光学院、豊島岡、攻玉社などが要注目です。
森上 横浜山手は、聖光学院の教務部長だった森先生が教頭に就任されることもあって、進学校化のイメージが高まっており、注目されています。
次に、首都圏の早稲田3校の動向予測をお願いします。
広野 <資料6>は、サピックス小学部の模試で、各校の第一志望者数の推移をまとめたものです。
最も注目されるのは、早大学院の第一志望者が、2009年9月の49名から、2010年11月は152名と、3倍近くに増えていることです。逆に、早稲田中は217名→113名と大幅に減少しています。早実はほぼ横ばいといったところです。他塾の模試の動向を見ても、ほぼ同様の傾向が見られます<資料7>。ただし、こうしたデータが公開されると、そのアナウンス効果で、直前に志望変更するといった事例も過去に見られました。そのため、断言はできないのですが、現時点では、早大学院は上位層も流入し、大幅に難化。早実は前年並みで、早稲田中はやや入りやすい状況が生まれると予想しています。
発展的な問題に対応できる応用力、思考力の養成がカギを握る
森上 では、この3校に合格するためには、どのような対策が必要になるのでしょうか。
広野 早稲田佐賀、早稲田摂陵を加えた5校の合格者が、サピックスに何年生から通ったのかというところでみますと、学校によって若干のバラツキはありますが、平均してみると、7~8割は4年生までに通い始めており、5年生から通った人を含めると95%に達しています。やはり、早稲田のような難関校に合格するためには、少なくとも4年生からは同じ塾に通い、系統立った受験対策を行う必要があるといえます。合格するために必要なポイントととしてまず大切なのは、4教科とも弱点のないように、バランスよく勉強することです。また、先ほど申し上げたように、算数で解き方、式を書かせない学校もありますが、その場合でも、論理的に考えなければ正答は導き出すことはできません。
必ず式をきちんと書いた上で考える習慣を身につけることが重要です。さらに、早稲田附属・系属校では、各教科とも基礎力だけで対応できる問題は少なく、発展的な問題が数多く出題されます。それに対応できる応用力、思考力の養成がカギを握るでしょう。入試問題の傾向はある程度一定しているので、過去問で習熟しておくことが肝心です。そうした学習を充実させるためには、公教育だけでは難しく、やはり塾に通う必要があると思います。同様の目標を持つライバルの存在が、頑張ろうという気持ちを育む効果も大きいのです。それぞれの目標に適した塾を選択することが、合格のための重要なポイントになるでしょう。

![[対談]2011年以降の早稲田附属・系属中学入試の流れ [対談]2011年以降の早稲田附属・系属中学入試の流れ](img/index_title07.jpg)