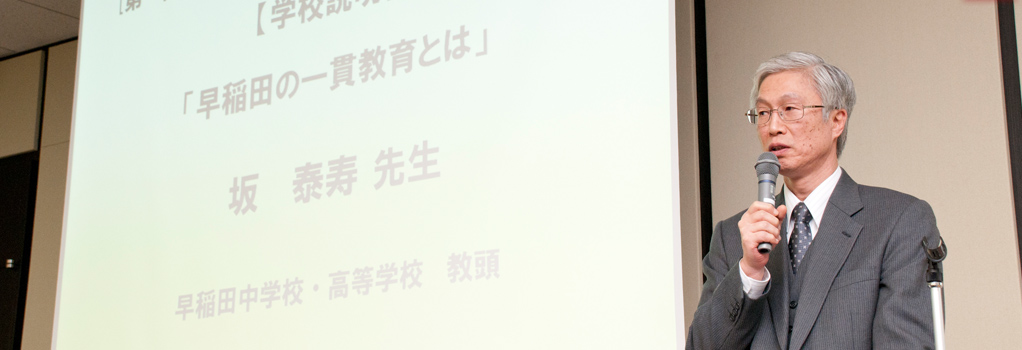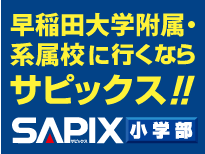早稲田への推薦入学者もそれ以外の生徒も同じハードなカリキュラム

本校は、早稲田大学への推薦入学者が約5割で、残りの5割は受験します。だからといって、両者を分けて教育することはいっさいなく、混在させたクラスで、同じ授業を受講します。しかも、その内容はかなりハードなものになっています。
中高一貫校のメリットを生かして、先取り学習を実施しており、中学2年次までに中学の履修範囲を終えます。それも、現行の学習指導要領に沿った内容ではなく、いわゆるゆとり教育以前の分野を加味しています。高校2年次までには高校の履修範囲を終え、高校3年からは大学入試の問題演習に入ります。それまで単元別に学んできたわけですが、大学入試問題は総合問題であり、様々な単元の考え方を総合的に利用して解くことが求められます。そうした思考力は、たとえ推薦で入学する生徒であっても、将来必ず必要になるものであり、大学入試問題を使って、全員に身につけさせたいと考えているわけです。
高校2年生から文系、理系に分かれますが、その後も文系で数学の授業が行われますし、理系でも国語は3年次まで必修です。これもまた、目先の大学入試だけでなく、大学入学後に必要になる学力はきちんと養成しようという方針によるものです。
自然や芸術に親しむ多彩な行事を実施

林間学校、サマーキャンプ、スキー学校、関西研修(修学旅行)、体育大会、興風祭(文化祭)など、行事が多彩なことも本校の特徴です。
とくにユニークなのが校外授業で、各学年で年間2~3回企画しています。本校では、原則として、学年主任とクラス主任(担任)が6年間持ち上がるスタイルをとっています(生徒は毎年クラス替えがある)。それによって、生徒の変化をきちんと把握することができます。この校外授業も、その時々の生徒の様子を踏まえて、ニーズを反映したものになっています。たとえば、利根川歩行は、7~8人のグループでひたすら利根川の河原を歩くのですが、その中でお互いに悩みなどを語り合う貴重な場になっています。芸術鑑賞も重視しており、中学生はミュージカル、高校生はオペラや歌舞伎などを観劇します。この際、貸し切りや、中高生用の特別な舞台を用意するのではなく、生徒は数名ずつバラバラに座り、一般の方々と一緒に鑑賞します。周りが正装している中で、慣れないネクタイをしめて、大人の世界をかいま見るわけです。もちろん、迷惑にならないように事前指導は徹底しています。当日は、皆緊張して、歩き方や言葉づかいまでいつもとは違ってきます。いい経験になっていると思います。
自分の学びたいことが明確な生徒が増加

本校では、生徒に自分の将来設計を考えさせる教育に力を入れています。高校1年次に、自分の性格を踏まえて、将来何をやりたいのかを考えさせます。2年次では、やりたいことが可能な学部・学科はどこか、調べ学習を行います。そして、3年次で、学力と照らし合わせて、具体的な志望大学・学部を決定します。
高校3年の11月の段階で、第一志望校が早稲田大学であれば、推薦の申請をしますが、この際に、こうした将来を考えさせる教育の効果があらわれていると感じます。医学部など、早稲田大学に設置されていない学部をめざす生徒が推薦申請しないのは当然のことですが、たとえ早稲田第一志望であっても、どの学部でもいいという生徒はほとんど見られないのです。それぞれ自分が学びたい分野が明確であり、自然と志望学部がばらけていきます。そのため、一部の学部では枠が埋まらない状況です。贅沢なことですが、方向性が明確な生徒たちの意思を尊重することの方が大切だと考えています。