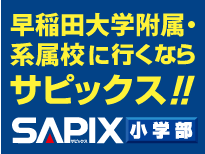中長期計画「Waseda Next 125」の3つの柱

近年、早稲田大学では大規模な教育改革を断行してきました。とりわけ2007年からは改革が加速しています。同年に迎えた創立125周年を「第二の建学」の出発点と位置づけ、21世紀におけるグローバルな早稲田大学を実現するための中長期計画「Waseda Next 125」を策定。「世界に存在感を示すことのできるWASEDA」を実現し、日本の地域社会において、あるいは世界のどこに行っても社会に貢献できる、叡知と気力を備えた人材の育成をめざしています。
教育改革の柱になっているのが、(1)早稲田の活力を維持しつつ「個別教育」へ、(2)「国際化」-早稲田からWASEDAへ、(3)「情報化」-個別対応した情報ネットワークの活用の3つです。
このうち、最も早くから改革が進行しているのが情報化です。1996年に全学の学生がインターネットのアカウントを持つようになっており、学内の約5000台のコンピュータを自由に使うことができます。メールアドレスは卒業後も利用可能です。24時間オープンしているPCルームは常に混雑しており、夜中でも勉強している学生が少なくありません。早稲田大学は全国で最も情報化が進んでいる大学であると自負しています。
早稲田の活力を維持しつつ個別教育へ

かつての早稲田大学には、学生の個性を尊重する一方で、自由放任のイメージもありました。現在では、個性重視の考え方に変わりはないものの、個別教育、少人数制教育に力を注ぎ、面倒見の良い大学に変貌しています。たとえば、全開講科目の70%が受講生50名以下で、マスプロ教育とは一線を画しています。ゼミも充実しており、約9割の学生が所属しています。2000年にはオープン教育センターを開設。学部の垣根を越えて、他学部の科目を自由に履修する体制を整えるなど、柔軟な教育システムになっています。
とくに個別的教育が展開されているのが「全学基盤教育」です。世界のどこでも活躍するためには、議論できる英語力を鍛えることが不可欠ということで、2003年から「チュートリアル英語」を開講。年間に約9000名が受講しています。学生4名に教育1名の少人数制で、教員は全員ネイティブあるいはバイリンガルです。週2回、授業があり、前回の授業の終わりに課題が出され、次回までに英語で書いてeメールで提出。教員がコメントをつけて返却します。会話力だけでなく、英語の文章力も身につくわけです。また、論理的な日本語文章力を養うために、2008年度からライティングセンターが、オンデマンドの8週間の授業を実施しています。毎週課題が出され、提出した文章に、大学院生がコメントをつけて返却する形です。さらに、文系学生に数学的論理性を養成するための講座も開講。こちらも8週間のオンデマンド授業で、毎週課題が出され、解答し、大学院生が添削指導しています。このように、学生一人ひとりにきめ細かく指導する体制を実現しているのです。
世界につながるキャンパス

現在、早稲田大学で学ぶ外国人留学生は約3500名。2007年に東大を抜いて、全国トップを誇っています。海外に留学する日本人学生も、2009年で1000名以上と、こちらも全国でトップです。
学内に設置されている国際コミュニティセンターは、外国人学生と日本人学生の出会いの拠点として機能しています。年間130以上の交流イベントが開催されており、一緒に活動する姿がよく見られます。
また、平山郁夫記念ボランティアセンターの活動も特筆されます。学生に社会貢献の意識を高めてもらうために多彩なボランティアプロジェクトが始動しており、毎年約1万2000名の学生が登録しています。墨田区での老人介護、荒川区の職業訓練のサポート、新宿区のゴミ清掃など、国内の活動だけでなく、ラオスの小学校建設支援、アルゼンチンのイグアス地域自然環境保全など、国際的な活動も活発化している点が特徴です。自発的に国際的な社会貢献に携わろうとする学生たちの姿勢を頼もしく感じています。