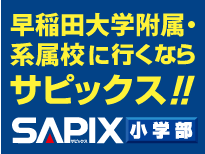「詰め込み教育」から「キャリアを形成する教育」へ

本校は1962年、大阪繊維学園として誕生。当初は高度成長期の技術者を養成する学校でしたが、その後、普通科全日制に衣替えし、地元に定着した中堅校として信頼されてきました。入学時の偏差値から10~15伸ばす学校という定評があったのです。けれども、そのために、高校2年次に文理分けを実施し、受験教科に特化した学習を強化していたことも事実です。1日7時限授業を基本とし、曜日によっては8~9時限授業も実施していました。いわゆる「詰め込み教育」、受験を通過することを第一義とする「通過儀礼としての教育」を行っていたわけです。その結果、大学入学後、専門課程に進んでから、高校で受験教科に特化した学習をしていたために、つまずくケースも出てきました。
2009年に早稲田の系属校となったのを機に、それまでの反省に立って、教育方針を大転換することにしました。「詰め込み教育」を排除し、「キャリアを形成する教育」をめざすことにしたのです。
専門教育からの遡及と、中等教育からの敷衍

本校の教育は、2つの方向性で再構築されています。1つは専門教育からの遡及です。つまり、将来、大学で専門を学ぶために何が必要かを見据えて、大学教育に連接した教育をめざしています。もう1つは中等教育からの敷衍です。内在する価値(「わたし」の「したいこと」)をじっくり考えて、自分なりのキャリアデザインを描く教育を重視しています。
具体的には、以下のような流れになっています。まず1年次では、自分は何が好きで、何を求めているのか、「わたし」の欲求から「わたし」を知ることが目標です。2年次は、他者や取り囲む社会との関わりの中で、「わたし」を考えていきます。3年次は、自分のしたいことが、社会においてどのような欲求につながっているのかを理解し、4年次では自分の資質を踏まえて、「したいこと」を「できること」に発展させます。5・6年次では、具体的なキャリアを描き、学部・職業選択につなげていきます。各段階において、早稲田大学のボランティアセンター、国際コミュニティセンター、キャリアセンターなどの協力を得て、適切なアドバイスを受けるなど、充実した内容になっています。たとえば、4年次には、コミュニティセンターの協力で、外国人留学生が本校を訪れ、対話することで、世界の中で自分にできることを何かを考える貴重な機会になっています。
個人カルテや学習支援センターなどによる学力保障

学力保障に関しては、個人カルテを作成しています。これは、毎朝実施する朝テスト、定期考査、模試の成績を一元管理しているもので、このツールを活用することで、教員は一人ひとりの生徒の情報を共有することができます。それによって、きめ細かな指導が可能になるわけです。
また、学習支援センターでは、個人カルテを参考に、生徒個々の学習動機を掘り起こし、自習計画のデザインを支援しています。同センターには、70席の自習室、30台のコンピュータがあり、eラーニングのシステムも備えられており、自学自習に活用されています。5教科の教員が常駐し、いつでも質問に応じています。