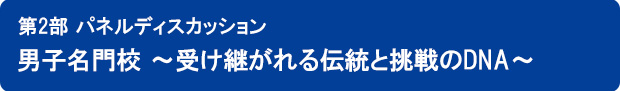「自由」のルーツと果実 ~ 自分たちでやるから成長する

髙宮 第2部では、3校が名門校として社会で活躍する人材を輩出し続けている背景や、これからの時代をリードする子どもたちに必要な力などについてお話を伺っていきたいと思います。最初のテーマは「自由」についてです。3校とも自主性を重んじる学校ですが、慶應普通部では「自由」についてどのようにお考えですか。
荒川 普通部は男子の単一性ということもあり、とても明るい雰囲気です。生徒が気軽に教員に話し掛けてくるなど生徒と教員の距離も非常に近いように感じます。しかし、自由であっても、何をやってもいいということではなく、福澤先生の言葉に「気品」とあるように、守るべきところは守っています。校則らしいものは紙1枚程度しかなく、「髪の毛は端正にしなさい」「黒の短靴を履きましょう」という感じです。個別の案件は生徒と対話をしながら対応しています。本人の意思や、やりたいと思っていることを伸ばす、そういう環境にあると思います。
髙宮 武蔵も自由な校風で知られていますが、そのルーツについてお聞かせください。
梶取 武蔵の自由は何かと考えると、やはり「学問の自由」だと思っています。生徒たちがどんな馬鹿馬鹿しいことを言っても、われわれはそれを馬鹿にしないで付き合います。本校の算数の入試では書くスペースを大きく取っており、そこには何を書いても構いません。われわれはそこに書かれたことを全部読み解きます。どんな答案でも、丁寧に読みます。学校行事の多くは生徒主体で行っています。もちろん生徒は失敗をします。記念祭(文化祭)で、冷蔵庫の到着が遅れて、模擬店で販売する予定だった冷凍食品をすべてだめにしたことがあります。そうした失敗を含め、われわれ教員は生徒たちの活動を見守るというスタンスをとっています。
髙宮 ありがとうございます。早大学院は「自由」についてはどうお考えですか。
本杉 自由というのは、味わわなければわからないという考え方があります。自由を味わうことで、初めて本当の自由の使い方がわかってきます。本学では、自由というのはどういうものかを体験して、味わいながら理解していく、そういうプロセスを大事にしたいと考えています。体育祭、校外研修などを自分たちで作り、経験していくなかで、自由を行使すると、価値あるものが生まれ、しかも楽しいということを学びます。自由に関する指導でいえば、生徒との会話を大切にしています。生徒はこれをしていいかと聞いてきます。そのとき、なぜそれをしたいのか、それをやることでどういうことが起きるのか会話をしながら一緒に考えます。そのうえで、生徒たち自身がこれはやる、これはやらないということを決めます。そうやって「考えながら自由を行使できる人」に育てていきたいと考えています。
 中1全員が参加する武蔵の「山上学校」。自分たちでコースを決めて、道を探しながら歩く
中1全員が参加する武蔵の「山上学校」。自分たちでコースを決めて、道を探しながら歩く高宮 自由な環境を通して、どういったことを学んでほしいとお考えですか。
梶取 生徒たちに任せていると、多くは失敗することもよくあります。しかし、その失敗は生徒にとって大きな財産になります。失敗させないようにと、われわれ大人が先に口や手を出すと、生徒は貴重な学ぶ機会を失ってしまいます。一生懸命やったうえでの失敗は財産です。私は、失敗の数が多ければ多いほどその子は成長すると思っています。たとえば、本校では中1の7月に山上学校という行事があります。生徒たちが自分たちでコースを決め、教員は生徒たちの後ろをついていきます。教員は地形を熟知しており、生徒が道を間違えるとすぐわかるのですが、よほどのことがないかぎり黙っています。生徒は道を間違えたことに気付くと、一生懸命に考えてグループで力を合わせてなんとかしようとします。生徒に任せることで、生徒たちに考えさせる。その経験が大事なのです。
本杉 本校も同じように中1のグループ活動で校外研修があり、自分たちでルートを作って動きます。自分たちでやるので、何かしら失敗します。そうすると、なぜ道がそれたのか、計画がどうだったのか、仲間内で議論になり、そして自分たちで解決していきます。そうやって次の機会には、失敗してもそれをどう立て直していくのか、その先の新たな挑戦をどうやればいいかを考えるようになります。すると、あれも知りたいこれも知りたいと知識欲が出てきます。そのように、失敗は自分から学びをつくる動きにもつながるように思います。
荒川 9月の労作展が終わると、すぐに来年に向けて動き出す生徒がたくさんいます。それを見ていると、「やらせる」「やらされる」のではなく、自分たちで進んで取り組むことがいかに大事かがわかります。中学生の男の子は、一度はまると一生懸命に取り組むので、力の入った楽しい作品も多く見られます。ぜひ一度足を運んでいただければと思います。
学びの「生産性」? ~ 無駄は無駄ではない
髙宮 最近、テクノロジーを使って教育に変革をもたらす技法としてEdTech(エドテック)という用語をよく耳にします。今年の6月に経済産業省が発表した提言でも、学びの生産を上げる教育イノベーションについて触れていました。「学びの効率性」についてはどうお考えですか。
本杉 授業を含めてさまざまな場面で新しいテクノロジーを用いていますが、「適切な場所で使おう」と考えています。効率ということでいえば、学院生は1円にもならないことを一生懸命やるとよく言われます。しかし、そういう無駄な体験が実は重要だと思っていて、「生産性」ということばには違和感があります。課題の解決には深い知識はもちろん、さまざまな要素が求められます。効率性を考えるだけでなく無駄も経験しながら広い基盤を備えて人間の幅を広げ、協働しながら次なる課題に挑戦してほしい、そう考えています。
高宮 慶應普通部では早くからプログラミング教育を導入されています。テクノロジーの活用と生産性という点ではいかがお考えですか。
 慶應普通部では、科目によってはコンピュータやタブレットを用いた授業も行われている
慶應普通部では、科目によってはコンピュータやタブレットを用いた授業も行われている荒川 情報端末を使うと、たとえば生徒40人それぞれの意見を画面で一度に表示できます。生産性ということではなく、生徒の個人の意見を授業に活用していくという意味で、重要な機能だと考えています。そうした機器を使った取り組みはかなり浸透しており、いろいろな教科で使っています。一方で、たとえば理科では毎週実験を行い、必ずレポートを書かせます。効率とはまったく違った観点から、特に中学段階の生徒にとっては手を動かしながら学ぶことはとても大切だと考えています。
高宮 梶取先生、リベラルアーツという観点からはいかがですか。
梶取 教育に関するいろいろな提言はきちんと受け止めています。そのうえで、学校が何をすべきかを考えています。これから人工知能が急速に進化します。たとえば音声の自動翻訳は今でも相当なレベルにあり、これから「スキル」の部分ではほとんど人間の手はいらなくなってくると思っています。コンピュータをはじめいろいろなテクノロジーは当然必要で、任せる部分は任せたほうがいいでしょう。そうではなく、人でなければできないこと、たとえば機械が訳したものを見て外国人と考えをやりとりすることなど人と人との関係は残ります。EdTech研究会などの提言も大事ですが、それらをどう利用するかが人間に問われています。考えもなしに利用することはいいことではありません。本校の理念の一つである「自ら調べ自ら考える」ことはますます重要になってきます。効率性も大事ですが、それだけではすぐに研究成果が出ないことはだめだとなります。無駄のまま終わる研究もあるでしょう。しかし、そういう研究があるからこそ、ノーベル賞を受賞する研究者も生まれるのです。無駄は無駄ではありません。効率を考えながらも効率だけには引っ張られない。そういうことがわれわれ教員だけでなく、社会に求められているのだろうと思っています。
グローバリゼーション ~ 異質な価値観を肌身で感じる大切さ
髙宮 それでは3つめのテーマ、グローバリゼーションに移りたいと思います。ボーディングスクールという、アメリカの全寮制の学校の説明会を行うと、たくさんの保護者の方たちが集まり、その関心の高さが伝わってきます。福澤先生も根津先生も大隈先生もグローバルという大きなうねりのなかで私学を立ち上げられました。あらためて学校としてグローバリゼーションをどうとらえ、どう対応されているかを教えてください。
荒川 高校段階では10スクールと呼ばれる名門のボーディングスクールへの派遣ということでかなり力を入れています。ただ中学段階では、3年間の普通部を1年間離れて、違う学校の教育を受けることは時期尚早と考えておりますので、中学時は準備にとどめて、高校段階でそのような交換プログラムに参加することを推奨しています。国際交流プログラムではフィンランドとオーストラリアがあり、こちらから派遣するとともに留学生の受け入れも行っています。やはり国際プログラムは非常に効果があると感じています。実際に触れ合うことで、生徒たちは「コミュニケーションには何より伝える気持ちが大切だ」ということを理解して帰ってきます。文化交流を通して、世界の中での日本の立ち位置なども考えるようになり、こうした経験が将来、国際的に活躍するために役立つように思います。
梶取 グローバルについて、私は次のように考えています。グローバル化とは自分と違った環境、宗教、地域、思想などを理解できること。つまり国内でもグローバルなんです。本校では、総合講座という名称で、北海道、対馬、沖縄などにも生徒を連れていきます。ふだんの学校生活と違う中でいろいろなことを学ぶ、これも私のなかではグローバル教育です。海外に関しては、韓国、中国、フランス、ドイツ、オーストリア、イギリスの学校と提携していて、長いと2か月間、生徒を単独で研修に出します。教員はついていきません。ほぼ同じ数だけの生徒がそれぞれの国からやって来ます。また、昨年の夏、アメリカ東海岸のハーバード大学、コロンビア大学、MITなどを視察しました。現地で学んでいる日本人留学生が口々に言っていたのは、自分たちに足りないのは語学力ではなく書く力だということでした。東大などを卒業した学生たちなので、少し差し引いて考えないといけませんが、「聞く・話す」は慣れてくればできるようになるが、書く力が圧倒的に足りないと言っていました。一方で、彼らを見て思ったのは、学ぶことが大好き、研究が大好きということ。中学・高校時代に自ら学ぶ姿勢を育てることが本当に大切だとあらためて感じました。
本杉 講演でもお話ししましたが、大隈重信自身、「世界中の人と一緒に真理探究することが世界平和につながる」という考えを持っており、本学院でもそうした方面には力を入れています。大事なのは、異質な人間同士が、相互尊重、相互リスペクトしながらつながるということなのだろうと思います。そのためには本物の体験をするしかありません。中学部では夏にオーストラリア語学研修を実施しています。また最近目立つのが、高校で取り組んでいるプログラムに中学生が積極的に参加しようという動きです。高校では、お互いの文化を知ることから始めて地球的な課題について探究をし、意見交換をする国際プログラムが進んでいます。こういう高校生の動きを中学生が見て、高校でシンポジウムに参加するために、中学段階から自分なりに調べ学習をして準備をしています。そうした思いに応えるためにも、本物の国際交流を行う機会をできるだけ用意したいと考えています。
社会リーダーの育成 ~ 当事者意識に基づく行動にエールを
髙宮 これまで多くの社会的リーダーを輩出されてきた3校ですが、どういう仕組みがリーダーとしての人間力を育み、自覚を芽生えさせてきたのか。またリーダーにはどういう力や資質が必要なのか。その辺りのお話をお伺いできればと思います。
梶取 3校は、真の意味のエリートを育てる学校だと思います。世間では、エリートというとネガティブなイメージでとらえられがちですが、エリートとは、自分のことだけを考えるのではなく、社会のことを考えられる人間です。そうした社会全体が見通せるリーダーを育てたいと思っています。リーダーにはどのような力が必要かというと、まずはタフな力です。さまざまな困難に出逢っても自分の力で解決していく力です。先ほどのアメリカでの学生の一人は、「馬力と信念が大切」と言っていました。それに加えて、何をやりたいかを持っていること、そしてそれを持ち続けること。何としてもこれがやりたいという、いい意味でのオタクであってほしいと思っています。
高宮 馬力と信念ということばを聞いて、ノーベル賞をとられた山中伸弥先生の「ビジョン&ワークハード」という言葉を思い出しました。本杉先生、いかがでしょうか。
本杉 リーダーというのは、社会が抱えている課題、あるいはさまざまなニーズを自分の問題として取り込み、解決策を見いだし、それを表現できる人物だと思います。最近、本校出身のある起業家の方と話をしたとき、社会をけん引していくのに必要な要素として彼が挙げたのは、根明(ネアカ)であるということでした。失敗してくじけても、暗くなってつぶれて終わらず、また前向きになれるタフな挑戦者であるということです。こうしたポジティブさがどこからくるかというと、失敗した経験の積み重ねによるものではないでしょうか。失敗を重ねるというのはそれだけ挑戦をしてきたということでもあります。何らかの社会課題に自分が持っている知識や技能すべてを使ってさまざまな人たちと協働して挑む。そういう全身全霊を懸けた挑戦体験の先に成功があり、リーダーとして認められていく。そういうことなのではないでしょうか。
髙宮 荒川先生、いかがでしょうか。
荒川 お話を聞いて、3校で共通な部分がたくさんあるように感じました。本校には「目路はるか教室」という、OBから話を聞く機会があります。実は学校というところはそれほど先進的なことを取り上げられる場所ではなく、教科の学びのなかでは最新の研究や論文に触れるのは容易ではありません。そうしたなかで、フレキシブルに最先端の知見を中学生に真剣に伝えてくれる機会が「目路はるか教室」です。大変な“熱量”で中学生に対応してくれる先輩たちの姿を見て、社会の先導者、リーダーというのはこういう人なんだ、自分たちもこういう人間にならないといけないんだという向上心を育てる機会にもなっています。たとえば私の選択授業で、慶應義塾大学の准教授になっている教え子から申し出があり、一緒に授業をやることになりました。武蔵、早大学院もそうだと思いますが、母校というだけで惜しげもなく後輩の力になろうとしてくれる、そういう先輩たちとのつながりこそが、次のリーダーをつくっていくうえで大きな役割を担ってくれている気がします。

髙宮 最後に、本日お集まりいただいた皆さんにメッセージを頂ければと思います。
本杉 子どもの成長段階に合わせて、共に歩む、共に走ることが大切かと思います。特に教員がそうなのですが、つい指示をしてしまいがちですが、彼ら自身が取り組んで、悩んで、仲間たちと議論をして、そこを突破して動き出すというプロセスをサポートしつつ伴走する。そうした姿勢で子育てしていただければ、お子さんの自立を促すことにつながるように思います。
荒川 慶應では「発育」という考え方もあって、子どもが本来育つような育ち方をするのを見守ってあげることができるといいかなと思います。中学生の男子のエネルギーはすごいものがあります。それをうまく良い方向に伸ばしてあげられればと思っています。
梶取 荒川先生からもお話がありましたが、やはり見守ることです。子どもたち、特に男の子はだらしないことが多いです。中1や中2の段階でしっかりした生徒はそんなに多くはありませんし、それは当然です。馬鹿なこともします。男の子はそういうものだと思ってください。小学校の男の子はいろんなことをしでかします。そこを温かく見てあげてください。よろしくお願いいたします。
髙宮 私たちサピックス代ゼミグループも、この3校のような名門校に進みたいという生徒さんの気持ちに応えられるよう、これからもしっかりとサポートさせていただきたいと思います。先生方、本日はたいへん貴重なお話をありがとうございました。