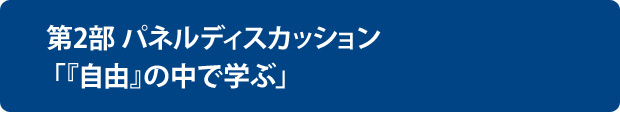自由な校風はいかに育まれたか?

髙宮 個性豊かな子どもたちの力を伸ばす「自由な校風」で知られる3校ですが、その校風がいかに育まれてきたのか、また、その自由な校風にどのような教育的効果があるのかをお聞かせください。
和田 本校は戦前の旧制中学の流れをくむ学校で、当時の自由な雰囲気が今も受け継がれています。しかし、自由ばかりで責任感や自律心がないと、奔放になり過ぎて困ります。たとえば本校には制服がないので、服装一つとっても自分で考えなければならない。ここから自主性が生まれます。自由は必ずしも楽なものではありません。芥川龍之介の『侏儒の言葉』には「自由は山巓(さんてん)の空気に似ている。どちらも弱い者には堪えることは出来ない」という一節がありますが、これはまさしくそのとおりで、自由を謳歌するためには、自己を律する心が必要です。これが本校の「自由」の特徴です。
大川 本校も戦前の創立ですが、学制改革で新たに中学校を設立したとき、英国のパブリックスクールをモデルとして新しいスタートを切りました。わたし自身も甲陽の卒業生ですが、中3の政治経済(公民)の授業で田中正造を研究したり、高校の英語の授業でポーの「アナベル・リー」という詩を何時間もかけて味わったりしたことをよく覚えています。生徒に自由があるのと同様に、教師にも教え方の自由があるのです。ただし「自由」は、教師にも生徒にも自己責任を求めます。ミヒャエル・エンデに『自由の牢獄』という小品がありますが、ここで主人公が叫ぶように「完全な自由」は「完全な不自由」なのかもしれません。自由を謳歌するためには“必然性に対する洞察力”が必要です。この3校なら、そんな自由が経験できると思います。
清水 本校はもともと働く若者を育む寺子屋のような学校でした。だから生徒を大人と見なして敬意を払いつつ、手をかけすぎず、良い意味で突き放した教育をしてきました。自由には「自分で自分の道を切り開かねばならない」という厳しさがあります。そんな厳しい自由を、われわれ教員も子どもたちも、共に背負っているといえると思います。
子どもたちに身につけてほしいこと
髙宮 今、子どもたちが身につけるべきものとは何でしょうか?
大川 本校の副校長の妙島秋男は、「教養が邪魔をする」という文章をある書物に載せております。たとえば、哲学の教養が豊富な人は、何か行動しようとするたびに「これでいいのか」という内的な問い掛けが生まれます。つまり、教養があるがゆえに、行動が邪魔されてしまうわけです。しかし、だからといって教養を排除すると、人は自分で考えず、流行に飛びつくようになってしまう。これはたいへん危ない世相だ、と。子どもたちが何を身につけるべきなのか―。それを考えるひとつのヒントになるのではないでしょうか。
清水 何かに役立つものだけを求める姿勢を捨てる」ことを身につけてほしいですね。何かにつけて有用であることが良しとされる世の中ですが、一見役に立たないことにも好奇心を持って打ち込んでほしい。いざ社会に出れば、世の中は不測の事態の連続です。イレギュラーに対応する力は、効率だけを追い求める姿勢からは育まれません。
和田 手前みそになりますが、本校の校是「精力善用、自他共栄」の精神を培って世に出てほしいと思います。そして社会でこれを実践し、周囲にも広げてほしいと思います。
髙宮 では、そのために、今の中高生にとって必要なことや解決すべき課題は何でしょうか? また小学生のうちに経験しておいてほしいことがあれば教えてください。
清水 「何かのために」という気持ちを捨てて、あらゆることに興味を持つことですね。そのためにも、周囲の大人が「これはやっても仕方がない」「そんなことをしていたらだめだ」ということばで、子どもたちの好奇心の芽を摘まないようにしてほしいと思います。
和田 本校には個性のとがった生徒が多いので、入学直後は互いに意識して軋轢が出ることがあります。しかし、成長とともに互いを認め合えるようになってくる。大人はそれを野放しにするのはだめですが、我慢しながら見守ることが大事だと思います。また、中学受験をめざすような偏差値の高い「偏った」子どもは、小学生時代は周囲のペースと自分のペースが合わず、やる気をなくしてしまうことがあります。そんなとき、親が適切にフォローして、やる気や好奇心を持続させてあげてほしいと思います。
大川 ひと言でいえば、「手を放せ、ただし目は離すな」ということですね。紆余曲折を経ながら、自分の道を歩む力を身につけさせるために、いちばん大事なのは家庭です。子どもの頃にいろんなことに挑戦し、失敗した経験も含めて、生活体験や生活実感をどんどん積ませてやってほしいと思います。家事のお手伝いでも、スポーツでも何でもよいので、勉強以外のことをたくさん経験させてあげてください。

清水 わたしは中学1年生の担任になったとき、黒板に『謝』という字を書きました。「謝」には「感謝」「謝罪」「謝絶」の意味がある。これらのことばがきちんと言える子であってほしい。ぜひ小学校時代に家庭で身につけさせてほしいことです。
溝端 わたしは中学受験合格をめざす小学生を塾で指導していますが、子どもたちは「好きだ」と思うと、一生懸命取り組むし、いろんなことを発見していきます。やはり小学生のうちから、そういう部分を伸ばしてほしいと思います。しかし、親御さんとしては、忙しいときに質問攻めにされると「ちょっと待って」と言わざるを得ない場面もありますよね。そんなときは、子どもの好奇心を思いっきりぶつける場として、ぜひサピックスを利用していただきたいと思います。
望ましい親子のかかわりとは?
髙宮 では、子どもを伸ばす、望ましい親子のかかわり方とはどのようなものでしょうか。
大川 子どもと一緒に楽しんでほしいですね。一緒に折り紙やあや取りで遊んだり、ピアノを一緒に弾いたり、ボールを蹴り合ったり…。進路についても、「甲陽に行け」と押しつけるのではなく、あくまで本人を主役にして、その決意を尊重してほしい。大学もそうです。自分で選んだ学校、自分で選んだ学部だという自負心を持たせてほしいですね。
清水 逆説的になりますが、「中学受験を突破するための理想的な親子関係は何ぞや、ということばかりを考えない親子関係であること」が大事だと思います。快適な衣食住をきちんと提供してやる。そして、子どもが勉強や学校生活で辛い思いをしているときは、しっかり話を聞いてやる。それだけで十分ではないでしょうか。わたしは大学受験を控えた高校3年生を持つ親御さんによく言いました。子どもが深夜まで受験勉強するからといって、「お前が起きているかぎり、わたしも寝ない」というような気持ちの悪いことは絶対にやめてくださいと。高校生にもなれば、親は最終的には「口を出さずに見守ること」しかできません。これはそのまま小学生には適用できませんが、いずれ子離れの時が来るのですから、親は親の人生を楽しむくらいの余裕を持ってほしいと思います。
和田 子どもが生まれ持った個性を曲げて、親が望む部分を無理に伸ばそうとするのはまずいと思います。わたしにも2人の子どもがおり、姉は早熟で弟は人見知り…と、まったく違う個性がありました。個性に合わせて、もちろん進路もそれぞれです。それでよかったと思っています。
溝端 中学受験をスポーツにたとえると、子どもが選手、教師はコーチ、親はマネジャーです。選手よりマネジャーやコーチが目立つのは明らかにおかしい。体調管理やスケジュール管理の面で、そっと支えてほしいと思います。
髙宮 最後に、受験生や保護者の皆さまにメッセージをお願いします。
和田 自由と自律の中で、日本人として身につけるべき教養を、知・徳・体を融合して学んでほしいと願っています。本校で学んでみたいというお子さんがおられましたら、ぜひチャレンジしてください。
大川 受験が近いお子さまは、ぜひ体調の管理に気をつけてあげてください。もし模擬試験で結果が悪くて、100点を取れるはずの子が70点だったら、あと30点も伸びしろがあることを喜ぶぐらいの気持ちで受け止めてあげてください。勉強のことは塾に任せて、家庭では子どもに逃げ道を作ってあげながら、見守ってあげてほしいと思います。

清水 受験生を全員迎えたいのがわたしたちの本心ですが、現実はそうはいきません。どれだけ一生懸命受験勉強に取り組んでも、合格か不合格かは紙一重。理不尽なことを12歳の少年につきつけることになります。それは運命として受け入れるしかありません。しかし、たとえ不合格でも受験勉強に励んだ事実は消えることはありません。「そのがんばりを誇りに思う」と、一度はしっかりお子さんに伝えてあげてください。そうすれば、子どもは安心して受験に臨めると思います。皆様とご縁がありますように願っています。
溝端 受験勉強を始める時期はお子さんによって違いますが、最終的に6年生の1月までがんばるのは同じです。今までのがんばりを誇りに思い、胸を張って受験に臨んでほしい。そして、入試本番でも普段どおりに力を発揮してください。