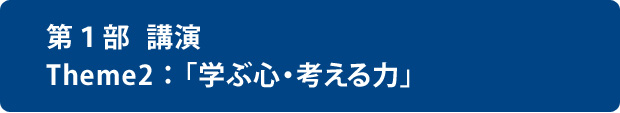教頭
この会場には受験を控えたお子さんを持つ方が集まっていると思いますので、本日は、お子さんにどういう姿勢で勉強をしてもらいたいかについて話したいと思います。
本校は1917年に創立しました。初代校長・伊賀駒吉郎が、その書籍のなかで「明朗・潑溂・無邪気」ということばを残していますが、まさにそれが校風として根付いています。本校が他の2校と大きく異なる点は、中学と高校が別の場所にあることです。学校案内パンフレットの表紙の写真は中学校の校舎の昇降口の風景ですが、ここは休み時間になると、子どもたちであふれます。1年生が中心となって「鬼ごっこ」をするのです。まるで小学生のようですが、実は彼らはそういう遊びをあまりしたことがないのですね。だから楽しくてしょうがない。子どもたちは遊ぶことで自由な発想を養います。ですからあえて校舎内で遊ぶことを良しとしています。
また、本校の高校には制服はありませんが、中学校には制服があります。制服は、少年時代にきちんとした装いを意識する経験を持てるという点でメリットがあります。一方、高校は服装が自由です。教師がそう決めたわけでなく、生徒会の要求によって制服が廃止されたのです。自主性に根ざした自由として、こちらも意味があると考えています。中学と高校は、部活動もそれぞれ独立していますし、文化祭や体育祭も別です。中高一貫校では、行事を高校生が仕切るのが普通ですが、本校は中学生がリーダーシップをとる機会が必然的に増えるので、自治とは何かを早い段階で考えることができます。
ところで、ノーベル物理学賞を受賞した物理学者・朝永振一郎が、出身小学校にこんな言葉を贈っています。
ふしぎだと思うこと
これが科学の芽です
よく観察してたしかめ
そして考えること
これが科学の茎です
そうして最後になぞがとける
これが科学の花です
これは非常によくできた詩です。まさに「不思議だと思い、よく観察して確かめ、考えること」こそが学びです。問題のパターンを覚えていくだけでは、本当に考えているとはいえない。パターンを超えた洞察力が必要なのです。また、思考を磨くためには五感からの刺激も大切です。皆さんのお子さんは、折り紙が好きですか。鶴は折れますか? 実は中学生になっても、紙をきちんと二つに折れない子がいます。経験がないからです。本校では、手を動かして遊んだり、音楽を聴いたり、演奏したり。五感をフル稼働させてさまざまな経験をさせることを大切にしています。
また、考えるためには言語が必要です。語彙力が増すと思考力も加速する。そのためにも読書は大事ですが、表面をなぞるように読んだだけでわかった気になるのはかえって危険です。名著を真剣に読み込まなければ本当の意味で身につかない。わたしは化学の教師ですので、中谷宇吉郎の『科学の方法』、朝永振一郎の『物理学とは何だろうか』はぜひ読んでほしい本です。文学では、ジョージ・オーウェルの『動物農場』、ウィリアム・ゴールディングの『蝿の王』なども少年の考えを深めてくれる良い本ではないでしょうか。

論語に「学びて思わざれば則(すなわ)ち罔(くら)し、思いて学ばざれば則ち殆(あやう)し」という言葉があります。 いくら勉強しても、自分で考えなければ本質が見えないし、逆に自分の考えばかりにこだわって周りを見ない人に世界は任せられない。パターンを学ぶことは大事ですが、未知の領域を永遠にパターンで埋めることはできません。パターンプラクティスという「各論的知識」と、全体を見て洞察する「総論的理解」のバランスが重要なのです。しかし、日本の教育は後者をおろそかにしているような気がします。学校とは役に立つことばかりを学ぶところではない。原点は学ぶ楽しさです。手段としての勉強ではなく、ただ学ぶことを目的にする。そんな勉強の仕方を身につけることが大切ではないでしょうか。
本当の自由は、こうすればこうなるという類いの"必然性への洞察力"がなければ手に入りません。そんな自由を持つ者こそが真のエリートなのです。「noblesse oblige」という言葉があります。思考力を持ち、高い位置にある者は責任も負わねばなりません。自分で疑問点を発掘し、自分で解決していこうとする大学生を、そして真のエリートを育てたいと思います。