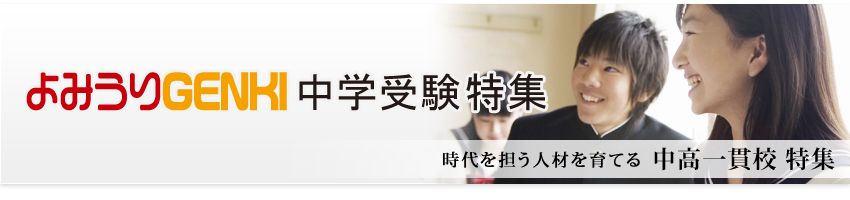
社会変革をもたらすのか

校長 野水 勉 先生
――生成AIの急激な進化が話題になっています。教育現場におけるその活用の可能性と、逆に注意すべき点について、どのようにお考えですか。
野水 生成AIがこれだけ普及してくれば、現実問題として使用にブレーキをかけるのは不可能です。使用を認めたうえで、生徒たちとも相談しながら、適正な使い方を考えていくというのが基本的な方向性になります。当然のことながら、宿題などを生成AIを使って解答しても、自分の力にはなりませんし、教員が見ればすぐにわかってしまいますから、そうした使い方は止めるように指導することになるでしょう。一方で、たとえば英作文の学習などでは、ChatGPTの活用が有効で、すでに多くの生徒が取り入れていると思われます。自分が書いた英文がネイティブスピーカーに近いレベルで添削されるからです。そうした生成AIのメリットと問題点を認識したうえで、十分に自分を律して、上手な活用を図ることが大切になると考えています。
海保 高い言語能力を持つ大規模言語モデルの出現は社会的な大事件であり、学校レベルで対応できる話ではないと、私は受け止めています。2017年にAI技術のブレークスルーが起こり、2022年11月には一般に公開されたわけですが、その後の浸透のスピードはすさまじいものがあります。これだけ日常生活に入り込んでいる状況で、使用制限をかけようという議論自体が、もはや時代遅れです。むしろ新たな時代が到来していることを大前提として受け止めて、このインパクトがどのような社会変革をもたらすのかを見据えながら、その中で何ができるのか、皆で知恵を出し合っていかなければならないと考えています。そして、社会の大きな転機に立ち会っている一人として興奮もしますし、また恐れも感じています。
――どのような「恐れ」を感じておられるのですか。
海保 私はAIの専門家ではありませんから、ただ漠然とした恐れを抱いているだけです。今の段階でも、情報端末を通して対話をしている相手が人間なのかAIなのかが判別できないほど、AIの対話能力は高い。しかもAIはセルフラーニングに近いこともできるようなので、デジタルアーカイブ化された人類の知的資産をどんどん学習して、ますます精度がアップしてゆくでしょう。近い将来、AIに対する人間の知的優位性が崩れ去ってしまうのではないか、という恐れです。
野水 生成AIについては、我々教員よりも、生徒の方がどんどん先を進んでいくでしょう。若い世代が柔軟に使いこなしていく中で、新しい世界を生み出してくれることを期待しています。
B2レベル以上が求められる

校長 海保 雅一 先生
――グローバルに活躍する人材を育成するために、英語教育の充実が重要になっていますが、現状をどのように見ておられますか。
海保 日本の英語教育が大きく転換したのは、1989年に改訂された学習指導要領からです。4技能のうち、「読む」「書く」以上に、「話す」「聞く」力の養成に重点を置いて、コミュニケーション力を高めようという方針が打ち出されました。その後、第3期教育振興基本計画(2018~2022年度)では、高校卒業時の英検®準2級以上の取得率を50%以上にするという目標が掲げられました。2021年度の取得率は46.1%ですから、残念ながらまだ達成はしていませんが、かなり近づいてきており、今年策定された第4期教育振興基本計画では、5年後の取得率60%以上をめざすというさらに高い目標が設定されています。一定の成果は上がっていると見ていいでしょう。ただし、一方で、大学の先生方からは、新入生の英語力が低下しているし、読む・書く力も不足しているという話も聞かれます。
野水 私が3年前まで在籍していた名古屋大学では、2015年頃から入学時にTOEFL ITP®(2017年に廃止されたTOEFL® PBTの形式を受け継いだ団体向けテストプログラム)の受検を課しています。そのスコアを見ると、年々少しずつ平均点は上昇しているようです。けれども、その平均点は、500点前後です。大学側がグローバルに活躍する人材として求めたいのは、TOEFL® PBTなら550点、TOEFL iBT®なら80点、すなわちCEFR(外国語学習者の習得状況を同一基準で評価する国際標準。A1・A2・B1・B2・C1・C2の6段階に分かれる)のB2レベル以上です。なぜなら、海外有力大学との交換留学の条件として最低限B2レベル以上が要求されるからです。もちろん、もっと低いレベルでも受け入れる大学もありますが、名古屋大学の学生が留学を希望する海外の有力大学となると、それだけの高いレベルが必要になるわけです。けれども、そのレベルに達している学生は数%で、それもかなり医学部に偏っているのが実情です。ちなみに先ほどの英検®準2級はCEFRのA2レベルです。その取得率がアップして、全体的には英語力が高まっていると言えるかもしれませんが、国立7大学のようなところでは全然物足りなく感じてしまうでしょう。
多様な形態の授業を展開
――両校には、それだけの高いレベルの英語力養成が期待されると思いますが、英語教育においてどのような工夫をされていますか。
野水 開成ではネイティブ教員を、専任で2名、非常勤で6名配置しています。日本人教員もネイティブ教員と英語で会話できる方々ばかりです。そうした教員団によって、早期から特に「話す」「書く」力を重視した授業を展開しています。たとえば中2では、2学期に自分で興味を持ったテーマについて原稿を書き、3学期に皆の前で3分間プレゼンテーションして、その内容を全生徒で評価する形式の授業があります。私も立ち会ったのですが、自分の趣味のほか、環境問題、政治問題など、テーマは多岐にわたり、しかも深く掘り下げた内容で驚きました。早期からこうしたトレーニングを積むことは、とても効果的だと感じており、実際、中3と高1で全員に課すGTEC®とケンブリッジ英語検定の結果を見ると、「話す」「書く」力のスコアが圧倒的に高くなっています。さらに、高校卒業時には、約半数の生徒がTOEFL iBT®80点、CEFRのB2レベルに到達していますし、約1割の生徒はTOEFL iBT®100点、CEFRのC1レベルに達しています。
海保 灘でも、全学年でネイティブ教員の授業を受けられる体制を整えています。ネイティブ教員の授業では、「発表」「やりとり」領域の指導が重点的に行われていて、プレゼンテーションなどの活動を通して生徒の発信力強化に役立っています。それから、言語習得には論理的に文章を組み立てる力が必須になりますから、パラグラフリーディング、パラグラフライティングにも力を入れています。
弱いことが大きな課題

――グローバル社会で活躍するために、英語力以外で必要になる力は何でしょうか。
海保 PISA 2018 の結果が気がかりです。数学的リテラシーはOECDの中で1位、科学的リテラシーは2位と好調でしたが、読解リテラシーは11位と低迷しています。「ラパヌイ島の森林が消失した原因を、ブログ、書評、ウェブ記事を読み比べて、エビデンスを抜き出して、自分の意見を自由記述する」という公表された読解力問題では、正答率がOECD平均を大きく下回ったそうです。つまり、事実と意見を区別したり、論理的に読解したり記述したりする力が弱いわけです。今回の全国学力テスト中3英語でも、「話す」の正答率が12.4%と最も低くなっています。特に壊滅的だったのが「日本の店でプラスチック製品の販売は止めるべきという考えに対して、英語で自分の意見を書け」という問題で、正答率1ケタでした。小学校時代から、SDGsのような社会的な話題について議論して、論理的思考力や表現力を高めるように努めることが大切になるでしょう。
野水 私は名古屋大学で、多様な国の大学と連携してプロジェクトを進める国際コンソーシアムの事務局長として運営に携わった経験があります。その際に感じたのは、様々な国の人々と協力するためには、多様な意見をとりまとめる力や、自分なりの企画を提案できる力などが要求されるということです。その力がなければ、単に周囲の考えを聞いているだけで終わってしまいます。その意味で、開成の文化祭、運動会などの学校行事は、教員の指示ではなく、自分たちで作り上げていく過程が、とても貴重なものだと感じています。まさに多様な意見が噴出する中で、リーダーシップを発揮して、意見をとりまとめて、方向性を見出していきます。人間力というか、ソーシャルスキルを高める、良きトレーニングの場になっているのです。私自身、開成の生徒だった頃に、学校行事の経験を通して成長できたという実感があります。
将来活躍する上での基盤になる

――両校とも、今お話にあった学校行事など、授業以外の活動を重視されています。その理由をお聞かせください。
海保 灘では、狭い意味での学力である「認知能力」とともに、「非認知能力」も育成することを心がけています。「非認知能力」は自主性、やり抜く力、共感力、想像力、リーダーシップなどの幅広い能力や特性を含んでおり、最近注目されている「ウェルビーイング」を高めるためには欠かせないものです。テストで高得点を取る能力だけ身につけても、進路目標の達成や、その先の人生における成功には、必ずしも結びつかないことを、私たち教員は経験的にわかっており、だからこそ、非認知能力の育成を重視しているのです。もっとも、認知能力は授業で育てることができますが、非認知能力は高めるのが難しい力でもあります。やはり授業外の仲間との集団活動等を通して培うのが効果的なのです。そこで、学校行事や部活動、生徒会活動などを充実させており、それが灘の変わらぬ学校文化にもなっています。
野水 学校行事や部活動、課外活動には、人間力を高めるだけでなく、ほかにもメリットがあります。たとえば文化部では、ひとつの分野を深掘りして、誰にも負けないような知識を備える生徒がたくさんいます。運動部でも、運動もできるし、学力も高い生徒も多く、それが次第に自分の個性になっていくケースが見られます。部活動はそうした自分の個性を発見する場でもあるのです。また、自主的な研究活動を行う生徒に対して、同窓会の協力を得て、研究費を支援する「ペン剣基金」という制度も設けています。研究計画のプレゼンテーションによって採択が決定し(数万円~約50万円)、研究後には報告書の提出を義務づけています。こうした自分の興味を掘り下げられる土壌があることが、将来活躍するための基盤になっている気がします。
海保 灘でも同様に、生徒の自主的な活動が活発です。掲示板に各種コンテストのポスターを貼っておくと、生徒たちが勝手に応募して、教員は受賞後に参加していたことを知ることも少なくありません。
対話、議論の機会を増やしてほしい
――最後に、保護者へのメッセージとして、小学校時代に取り組んでほしいことをお聞かせください。
野水 生成AIの脅威が大きな問題になっていることは確かですが、それを使いこなして、その先に人間らしい創造を実現するためには、いろんなことに好奇心を持って、自分なりに考える力を培うことが大切です。そのために、小学校時代にはぜひ、自然に親しんでほしいですね。自然現象の不思議を感じたときには、本などで調べて、自分なりに説明できるようにしておくといいでしょう。あるいは博物館、美術館などに出向き、先人の知の蓄積に触れるのもお勧めです。そうした経験を通して、興味が喚起されることで、将来、自分の個性を発揮できる分野が見つかることも期待できます。
海保 困難なことかもしれませんが、今後一段と言語能力を高めてくるであろう生成AIに負けない言語技術を持つことが重要になると思います。ヨーロッパの小学校では、自国の詩、演劇、文学、哲学などを題材にして、とことん議論する授業が設けられています。日本の小学校にはそうした授業がほとんどないのが残念ですが、先ほども申し上げたように、やはり小さい頃から、対話、議論の機会を増やして、言語技術を高めることが大切になると思います。
※英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

- 市川中学校・高等学校
- 栄東中学・高等学校
- 佐久長聖中学・高等学校
- 狭山ヶ丘高等学校・付属中学校
- サレジアン国際学園中学校高等学校
- サレジアン国際学園世田谷中学高等学校
- 渋谷教育学園渋谷中学高等学校
- 渋谷教育学園幕張中学校・高等学校
- 西武学園文理中学・高等学校
- 桐蔭学園中等教育学校
- 東邦大学付属東邦中学校・高等学校
- 東洋大学京北中学高等学校
- 東洋大学附属牛久中学校・高等学校
- 広尾学園中学校・高等学校
- 広尾学園小石川中学校・高等学校
- 明治大学付属明治高等学校・明治中学校
- 立正大学付属立正中学校・高等学校
- 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部・高等部
