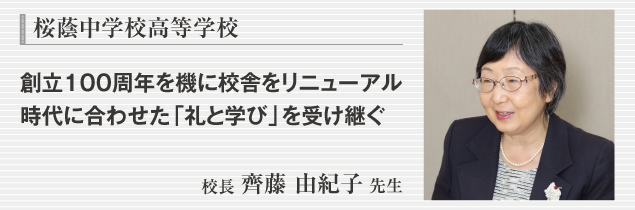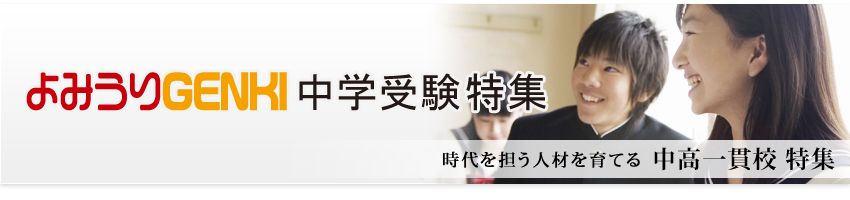
─私立 中高一貫校がいま、考えていること─

桜蔭学園は、関東大震災直後の1924年に東京女子高等師範学校(現・お茶の水女子大学)の同窓会「桜蔭会」によって創立されました。建学の精神に「礼と学び」を掲げ、品性と学識を備えている自立した女性の育成に取り組んでいます。
初代校長の後閑キクノは、「礼法」を体系的な学問として完成させた人物でした。そのため、この「礼法」は創立時から続く本校の伝統的な授業として知られ、今でも中1は週1回、立礼・座礼の仕方、物の受け渡し方などの基本的な立ち居振る舞いを学んでいます。なかには、ふすまの開け方やお茶の出し方、いただき方など、今の時代の子どもたちにはなじみの薄いものもありますが、あくまで大切にしているのは「相手を気遣う気持ち」です。正しいマナーや所作を知ることは、客人へのおもてなしの気持ちや、相手を不快にさせない言動について考えるきっかけになります。これからは国際化が進み、国籍や宗教の異なる人々とのお付き合いが増えることでしょう。そうした時にも、相手を気遣う気持ちがあれば、文化の壁を越えた親密な関係の構築ができるはずだと考えています。
相手を気遣う気持ちを養うことにおいては、コロナ禍での経験も大きな意味があったと思います。感染症に対する考え方が各家庭によって異なることを理解し、全員が安心して学校生活を送るためにはどうしたらよいかを考えなければならない場面が数多くあったからです。たとえ自分とは異なる価値観であっても理解を示し、相手の視点に立った解決策を模索することで、生徒たちは一回り大きく成長したように思います。

本校の特徴の一つとして、理系志望の生徒が全体の7割を占める点が挙げられます。もともと理数科目が得意な生徒が多いこともありますが、授業で積極的に実験を取り入れたり、天文気象部・物理部・生物部・化学部・数学部といった理数系のクラブ活動が充実していたりと、理系分野への興味を引き出す環境が整っているのも大きな要因だと思っています。また、順天堂大学や東京医科歯科大学との高大連携をはじめ、新潟大学や東北大学の教授による出張講義なども開いており、生徒たちに理系のキャリアをより具体的にイメージしてもらうための試みを数多く用意しています。
卒業生が自身の中高生活や現在の職業について語る、高1生対象のキャリア教育講演会も人気です。この講演会には、生徒たちと年齢の近い若い卒業生だけでなく、結婚・出産を経て、育児をしながら働いている30代から40代の方にも積極的に来ていただいています。「出産を機に仕事のペースを変えた」「夫と子どもを置いて自分だけ単身赴任をした」など、さまざまなエピソードを聞くことができ、生徒は非常に感銘を受けているようです。中高生が考えるキャリア観というと、志望大学や大まかな職業といったところで止まってしまいがちですが、大切なのはその先です。こうした卒業生のリアルな声を聞くことで、結婚や出産といったライフイベントを経験しても続けていける、柔軟な働き方があることを学んでほしいと考えています。
また、校内の放課後学習ルームでは、週に1回、卒業生である現役大学生のチューターが生徒の質問や進路相談に対応しています。勉強でわからないことがあるとき、教員をつかまえて積極的に質問できる生徒はいいのですが、そうでない生徒にとっては気軽に相談できるお姉さんのような卒業生の存在が心強いようです。この場所を上手に利用して、自学自習のリズムを身につけるとともに、卒業生とのつながりを活用して、自らのキャリアビジョンを描いていってほしいと思っています。

本校は来年で創立100周年を迎えます。その記念事業として、東館校舎の建て替えを行っており、9月末に竣工する見込みです。新しい東館には、地下1階に温水プール、地上1・2階に普通教室、3階に物理室・化学室・理科講義室、4階に体育館が入ります。最近は、プールを廃止する学校も少なくありませんが、本校では創立以来、水泳の授業を大切にしてきましたから、新しい東館でも迷わず存続させる判断をしました。温風で乾かす設置型のドライヤーを採用するなど、生徒たちがより快適に使えるような工夫を凝らしています。また、従来の東館に比べると、教室が1フロア分増えるので、空間的にも余裕をもって教育活動ができるようになります。さらに、西館と東館をつなぐ上空の廊下ができるので、校舎間の移動がよりスムーズになることも期待されます。今年の文化祭には間に合いませんが、来年の文化祭では、この新校舎を使って、理数系の5クラブが並ぶ名物企画「サイエンスストリート」を復活させたいと考えています。
受験生の皆さんは、それぞれがめざす学校に向けて一生懸命に頑張っていることでしょう。もしかしたら、「志望する中学に合格するまでの辛抱」と、歯を食いしばっているかもしれません。しかし、忘れないでいただきたいのは、勉強は中学受験で終わるものではないということです。中高生になっても、大学生になっても、社会に出た後も、学びはずっと続きます。まさにその入り口に立つ皆さんには、「楽しい」と思える勉強をしてほしいのです。何かを知ることは、本来は楽しいものなのではないでしょうか。そういう勉強を心がけていれば、その学びがきっと将来の自分にとっての力になると思います。

- 市川中学校・高等学校
- 栄東中学・高等学校
- 佐久長聖中学・高等学校
- 狭山ヶ丘高等学校・付属中学校
- サレジアン国際学園中学校高等学校
- サレジアン国際学園世田谷中学高等学校
- 渋谷教育学園渋谷中学高等学校
- 渋谷教育学園幕張中学校・高等学校
- 西武学園文理中学・高等学校
- 桐蔭学園中等教育学校
- 東邦大学付属東邦中学校・高等学校
- 東洋大学京北中学高等学校
- 東洋大学附属牛久中学校・高等学校
- 広尾学園中学校・高等学校
- 広尾学園小石川中学校・高等学校
- 明治大学付属明治高等学校・明治中学校
- 立正大学付属立正中学校・高等学校
- 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部・高等部